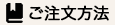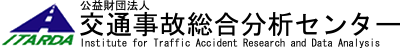2024年学会発表論文
一覧へ戻る
2024年学会発表論文
被害軽減・事故低減に向けた自転車事故の分析
【講演】日本機械学会 バイオエンジニアリング部門 「第24回傷害バイオメカニクス研究会」 (2024/2/16, 公開研究会)
講演者:河口 健二
近年の自転車利用の増加を受け、最新の事故データを用いて自転車事故実態を明らかにした。 まず、事故後24時間を超え30日以内に亡くなる30日死者を加えると自転車死者数が1.5倍にもなることが明らかになった。また、頭部傷害状況、ヘルメットの効果を分析した。 次に、自転車単独事故については、死亡では転落の多さと転落後の溺死の多さ、死傷では東京での顕著な増加を捉えた。さらに、自転車と歩行者との事故も増加が見られ、特に人口密度の高い都道府県が多い。最後に、乗用車と自転車との事故について、新しい車ほど事故が少なめになっていることが確認できた。ただ、同一モデルであればハイブリッド車の方が事故が多めであることが示唆された。 このように今回の一連の分析で、自転車関与事故の被害軽減・事故低減のヒントと今後の研究課題が得られた。
※本内容は2023年のITARDA調査研究発表会にて発表したものをベースとしており、日本機械学会よりその内容について特別講演の依頼を受け講演したものである。
Study on a method for reconstructing pre-crash situations using data of event data recorders and dashboard cameras
【学会発表】WCX SAE World Congress Experience 2024 (2024/4/16-18)
発表者 :松村英樹・杉山幹・岩田剛和
When investigating traffic accidents, it is important to determine the causes. To do so, it is necessary to reconstruct the situation in which the accident occurred as accurately and in as much detail as possible. This paper examines a method for reconstructing the circumstances that led one of the vehicles involved to the pre-crash situation using objective and diverse data recorded by an event data recorder (EDR) and a dashboard camera (DBC). The method consisted of first integrally calculating the vehicle’s traveling trajectory using the vehicle speed and yaw rate recorded by its EDR, each point along the trajectory being linked to the EDR data. The EDR data had the driver’s operation status (applying and releasing the service brake, etc.), the vehicle’s behavior (vehicle speed, etc), the operation status of the vehicle’s electronic control systems such as an autonomous emergency braking system (AEB). After combining the traveling trajectory with the images of the DBC, the trajectory was projected onto a road map around the accident site to create a reconstruction diagram. This diagram was then applied to the real-world accident. One of the vehicles in the accident was equipped the AEB. The analysis of the reconstructed accident situation showed that the Advanced Emergency Braking System (AEBS) of one of the vehicles was not designed to be activated in this collision scenario. Using this reconstruction method, objective and diverse pieces of information (collected by EDRs and DBCs) and traveling trajectories obtained from traffic accident investigations were projected onto a road map in a chronological and integrated way to reconstruct the pre-crash conditions as accurately and in as much detail as possible.
H. Matsumura, M. Sugiyama, T. Iwata., "Study on a method for reconstructing pre-crash situations using data of event data recorders and dashboard cameras ," WCX SAE World Congress Experience 2024, 2024-01-2891.
同乗者の有無と高齢運転者の人身事故頻度の関係
【学会発表】土木学会「第69回土木計画学研究発表会・春大会」(2024/5/25)
発表者:小菅英恵・田久保宣晃・稲田晴彦
本研究では,安全運転要因として同乗者の存在に着目し,各種運転条件下での同乗者の有無と,高齢運転者の人身事故頻度の関係性について加齢変化を考慮し探索的に検討することを目的とした.
ITARDA保有の全国乗用車運転者の3年間の人身事故項目ごと,運転者年齢層別に全年齢群に比べた単独運転に対する同乗者が居た事故のオッズ比と,95%信頼区間から相対的な事故頻度の高低を評価した.
結果,全年齢群に比べた単独運転に対する同乗者が居た事故の頻度は,[前期・後期高齢の運転者]において,私用目的の運転,午前11時~午後5時台,人口集中地区等の運転条件下で低く,反対に[18~24歳の運転者]において,業務目的を除くすべての運転条件下で高かった.
同乗者が居た事故の頻度が低下を示す運転条件を把握することは,高齢運転者の事故防止,安全運転支援の方法を議論するための基礎資料となる.
小菅 英恵・田久保 宣晃・稲田 晴彦(2024).同乗者の有無と高齢運転者の人身事故頻度の関係 土木計画学研究発表会・講演集(CD-ROM),69,ROMBUNNO.E11-3
車両取扱説明書にある先進安全機能の非推奨環境における衝突被害軽減ブレーキの効果分析
【学会発表】第69回土木計画学研究発表会・春大会(2024/5/26)
著者:山口大輔・高宮進
高度な自動運転レベル2に相当する「ハンズオフ機能」搭載車両を開発した自動車メーカー4社を対象に,車両の取扱説明書に記載された先進安全自動車の機能が正常に作動しない可能性がある道路構造・環境等(非推奨環境)を整理し,当センターの事故データにより分析可能な項目を抽出した.その結果,インターチェンジ,工事規制等が事故データに基づき効果分析が行える非推奨環境として抽出できた.
また,非推奨環境において,衝突被害軽減ブレーキ(AEB)搭載車と非搭載車の保有台数あたり事故件数の削減率の大小を比較することで,非推奨環境におけるAEB搭載車による事故削減効果を確認した.その結果,変速車線,トンネル,工事区間,落下物,自然渋滞,事故車・故障車等に影響を受けた事故では,AEBによる追突事故の削減率が低いことがわかった.
記憶力・判断力が少し低下した高齢運転者に対する技能検定手続きを用いた運転指 導の評価と応用――単一事例実験のABABAB デザインによる行動変容の効果検証(2)――
【学会発表】日本交通心理学会「日本交通心理学会第89回大会」(2024/6/1)
発表者:小菅英恵・岩城直幸・外川佑
我々は,記憶力・判断力が少し低下した高齢運転者に教習所で反復訓練を実施後の運転変化について,新規免許取得者の検定手続きを適用し評価している.本研究では,現状は定まった方法が存在しない高齢運転者への運転指導による行動改善や変容を評価する方法として,新規免許取得者の運転評価手続きの応用可能性を考察する.
介入はABABABデザインを用い,運転変化を効果量から考察した結果,安全不確認など,本人が苦手とする運転は,個別指導により,改善,維持の効果を示した.
新規免許取得者の検定手続きは,高齢運転者自身が苦手,不得意とする運転技能を細かく評価可能であり,指導による高齢運転者の運転の改善,行動変容の評価方法として応用可能と考えられる.
小菅 英恵・岩城 直幸・外川 佑(2024).記憶力・判断力が少し低下した高齢運転者に対する技能検定手続きを用いた運転指導の評価と応用――単一事例実験のABABAB デザインによる行動変容の効果検証(2)―― 日本交通心理学会第89回大会発表論文集,48-51.
幹線系道路における、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)の追突事故削減効果
【講演】交通工学研究会:第108回交通工学講習会(東京)「シン・交通事故対策 ~交通安全マネジメントのこれまでとこれから~」(2024/7/9)
講演者:高宮 進
交通事故防止と交通事故時の被害軽減に向けて、「人」「道」「車」の三要素それぞれから交通安全対策が進められてきた。「車」については、先進安全自動車(ASV)の検討が進められており、技術がドライバーの安全運転を支援することによる、事故の軽・減が期待される。ここでは、先進安全自動車に搭載される技術のうち衝突被害軽減ブレーキ(AEB)について、一般国道での追突事故削減状況の分析結果を紹介する。
また講演後のパネルディスカッションにおいて、講演内容を踏まえて、道路交通環境的側面からの「今後の交通安全対策」について討議する。
高齢運転者の安全研究から見えたこと
【講演】日本応用心理学会 第90回大会「交通社会の諸問題を質的・個性記述的に解決する意義と方法」自主企画ワークショップ(2024/8/27-28)
講演者:小菅英恵
高齢者の「健康」「安全」「モビリティ維持」は,我が国の重要な社会課題であり,ITARDAでは,近年,教習所と共同で,認知機能が低下した高齢者個人への安全運転指導の介入研究を行なっている.高齢運転者は,独自の運転経験と個別の加齢変化の相互作用から個人差が極めて大きく,そのため,運転者教育の現場では,ヒューマンファクタの普遍法則だけでは,高齢運転者の理解や,個別対応となる問題改善に当てはめることが出来ない.
事故を起こさない運転を遂行するのは一人一人の運転者である.事故防止や交通安全の研究において,運転改善のため介入した相手の体験や意識にも目を向け記述することは,実学を目指す交通心理学において,介入相手の理解だけでなく,どのような介入手法が効果的なのかの見極めや,別の事例の行動等改善の具体の手がかりを得ることにもつながるのではないか,と考えている.
大谷 亮・小菅 英恵・中西 誠・中野 友香子・横井川 美佳(2024).交通社会の諸問題を質的・個性記述的に解決する意義と方法 日本応用心理学会第90回大会発表論文集,90,ⅻ.
近年の乗用車対自転車の出会い頭事故の特徴と自転車AEBの効果の分析
【学会発表】自動車技術会 2024年秋季大会 学術講演会(仙台, 10/23-25)
(セッションNo. 141 事故分析, 講演No. 266, 10/25(金))
発表者:河口 健二
近年の乗用車は対車両のAEB(被害軽減ブレーキ)の普及で追突事故が減少し、出会い頭事故が最多となり、その事故の中で自転車の傷害が最多である。この出会い頭事故について様々な視点から分析し、事故の要因等の特徴を洗い出した。1当自転車の法令違反は、信号有交差点では信号無視が88%と最多であり、信号無交差点では一時不停止が54%で最多となっている。1当自転車の死亡割合は1.01%で2当自転車の4倍以上、死亡重傷割合は15.6%で2当自転車の約2倍となっている。自転車が1当の時の方が乗用車の速度が高いことも要因の一つである。
対自転車のAEBは出会い頭で10%前後、右折時で20%強の死傷事故低減効果が見られた。ただ、ハイブリッドエンジンや電気自動車は自転車との出会い頭事故が通常のエンジンの車と比較し多めとなっている。これは、出会い頭事故の乗用車の速度が低いことと低速での走行時の音が小さいため自転車が気づきにくいことが要因ではないかと考えられる。さらなる調査・研究・対策の検討が望まれる。
掲載: 2024年秋季大会 学術講演予稿集 セッションNo. 141 講演No. 266
文献番号2024266
高齢運転者の自記式調査における項目無回答の低減に向けた調査票デザインの検討――質問項目のスキップ表示と回答欄の順序・配置の改良による回答傾向の変化――
【学会発表】日本交通科学学会「第60回日本交通科学学会総会・学術講演会」(2024/9/3)
発表者:小菅英恵・檜田容子・宮崎由規・新田裕介
発表者:小菅英恵・檜田容子・宮崎由規・新田裕介
我々は,70歳以上高齢者講習受講者を対象に,加齢特性やデザインを考慮した自記式調査票を用いた共同研究を実施している.自記式調査票のどのようなデザイン面が高齢者の回答に影響を及ぼすのかは不明な点が多い.本報告では,高齢者から高精度なデータを収集可能とする調査票を検討するため,自記式調査票の一部デザインを改訂し,改良前と改良後で得た高齢受講者の回答傾向を比べる.
結果,分岐質問の改良により,高齢者本人の無回答が低減した.分岐は基本型に比べ認知的負荷が大きくなるため,高齢者向けの自記式調査票で無回答を回避するには,分岐の設計や質問配置により,高齢者の認知負荷の軽減や分かりやすさを促す工夫が必要である.
小菅 英恵・檜田 容子・宮崎 由規・新田 裕介(2024).高齢運転者の自記式調査における項目無回答の低減に向けた調査票デザインの検討――質問項目のスキップ表示と回答欄の順序・配置の改良による回答傾向の変化―― 日本交通科学学会誌 第60回日本交通科学学会学術講演会講演集,24(補刷),45.
実車指導による高齢運転者の老性自覚の変容――安全運転教育効果と地域の安全性に関する研究(1)――
【学会発表】日本交通心理士会「日本交通心理士会第21回ぐんま大会」(2024/11/16)
発表者:小菅英恵・宮崎由規・新田裕介・藤田佳男
発表者:小菅英恵・宮崎由規・新田裕介・藤田佳男
実車指導を受けた高齢運転者は,どのように自身の運転の老いを自覚しているか,また,運転の老いの自覚のしやすさ(しにくさ)が,日ごろの運転を含めた生活状況とどのように関係するかは十分に明らかではない.本研究では,高齢者講習受講者を対象に,アンケートで得た実車指導直後の運転の老性自覚の回答を調査した.
結果,実車指導後の老性自覚の項目間相関より,受講後,特定の機能低下だけを意識
するよりは,全般的な老化の認識から運転の老いを自覚しやすいことが示された.また,受講前にヒヤリハット体験が無い受講者は受講後の老性自覚が弱く,年齢や運転頻度,外出頻度,歩行頻度との関係はほぼ見られなかった.高齢者の運転の老性自覚には,運転のリスク認知が重要な要因である可能性が示された.
小菅 英恵・宮崎 由規・新田 裕介・藤田 佳男(2024).実車指導による高齢運転者の老性自覚の変容:安全運転教育効果と地域の安全性に関する研究(1) 日本交通心理士回第21回大会発表論文集,1-4.
高齢者講習受講者の運転行動特徴分類の試み――基準行為の有無データに対するk-modesクラスタリングを用いて――
【学会発表】日本安全運転医療学会「第8回日本安全運転医療学会学術集会」(2024/12/15)
発表者:小菅英恵・外川佑・岩城直幸
本研究では,『高齢者講習』受講者の行動特徴を探るため,同乗する教習指導員が加齢で維持が出来ていない運転能力を確認する『運転技能検査』と同様の方法により,教習所コース内の決められた地点を通過した際に基準行為が出来たか-出来なかったか(不履行)で評価された二値データを用いて行動分類を試みた.
対象は新潟県A教習所の高齢者講習受講者男女829名とした.解析は非階層クラスター分析の一種であるk-modesクラスタリングを用いて,基準行為不履行の高齢運転者を4クラスターに分類した.
結果,「段差乗り上げ」不適が全員該当するクラスター(C1とC2)が存在した.また,走行時に指導員から補助ブレーキ等の処置を7割の者が受け,かつ,2回は処置があった者が2割存在するクラスターは,見通しの良い「一時停止交差点」で不停止の者が7割該当していた(C3).今後はこれら不履行(運転エラー)の特徴が,どのような背景要因や属性と関連しているかを調査する必要がある.
小菅 英恵・外川 佑・岩城 直幸(2024).高齢者講習受講者の運転行動特徴分類の試み――基準行為の有無データに対するk-modesクラスタリングを用いて―― 第8回日本安全運転医療学会学術集会抄録集,49
安全運転継続の対策強化と支援の仕組み化――事故予防と運転者対策のあり方――
【講演】第8回日本安全運転医療学会学術集会「安全な交通社会実現への多角的アプローチ」シンポジウム(2024/12/15)
講演者:小菅英恵
運転者の事故は,交通システム全体の中で生じた環境不適応の行動の結果であり,運転計画や設計,安全教育や技能訓練,運転条件の調整等により防ぐことが可能である.近年,高齢運転者の事故が懸念される一方で,自動車の運転は,高齢者の健康維持と自立した生活の確保に有益であることが示されている.
運転者の対策は,道路安全に限らず人々の健康と生活の維持を含め一体的に計画し,予防の点から可能な限り安全運転歴を長く保つための対策を推進し,個々の運転者に応じた安全運転支援につなげる仕組みが必要である.行政と,運転訓練・指導や医療等の専門サービスが可能な関係機関が連携し,運転者が高齢になる前から,運転キャリア設計や,安全運転行動の定着と身体・認知機能等低下を防ぐ取り組みが求められる.また,EBPM と運転者の事故リスク評価(C/A)-対策立案(P)-安全運転支援の実践(D)-効果評価(C/A)の体系的運用が重要である.
小菅 英恵(2024).安全運転継続の対策強化と支援の仕組み化――事故予防と運転者対策のあり方―― 第8回日本安全運転医療学会学術集会抄録集,41